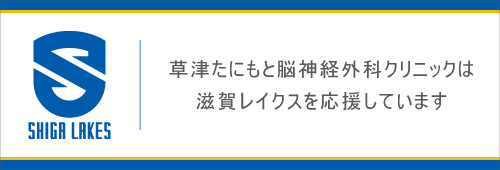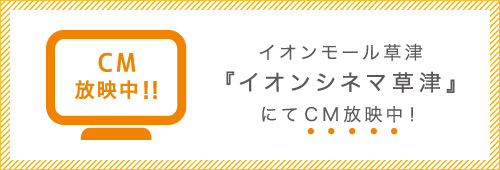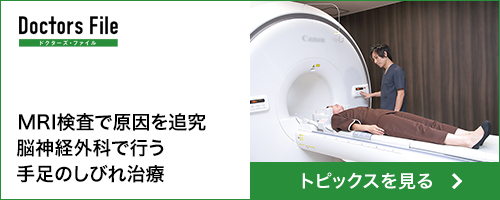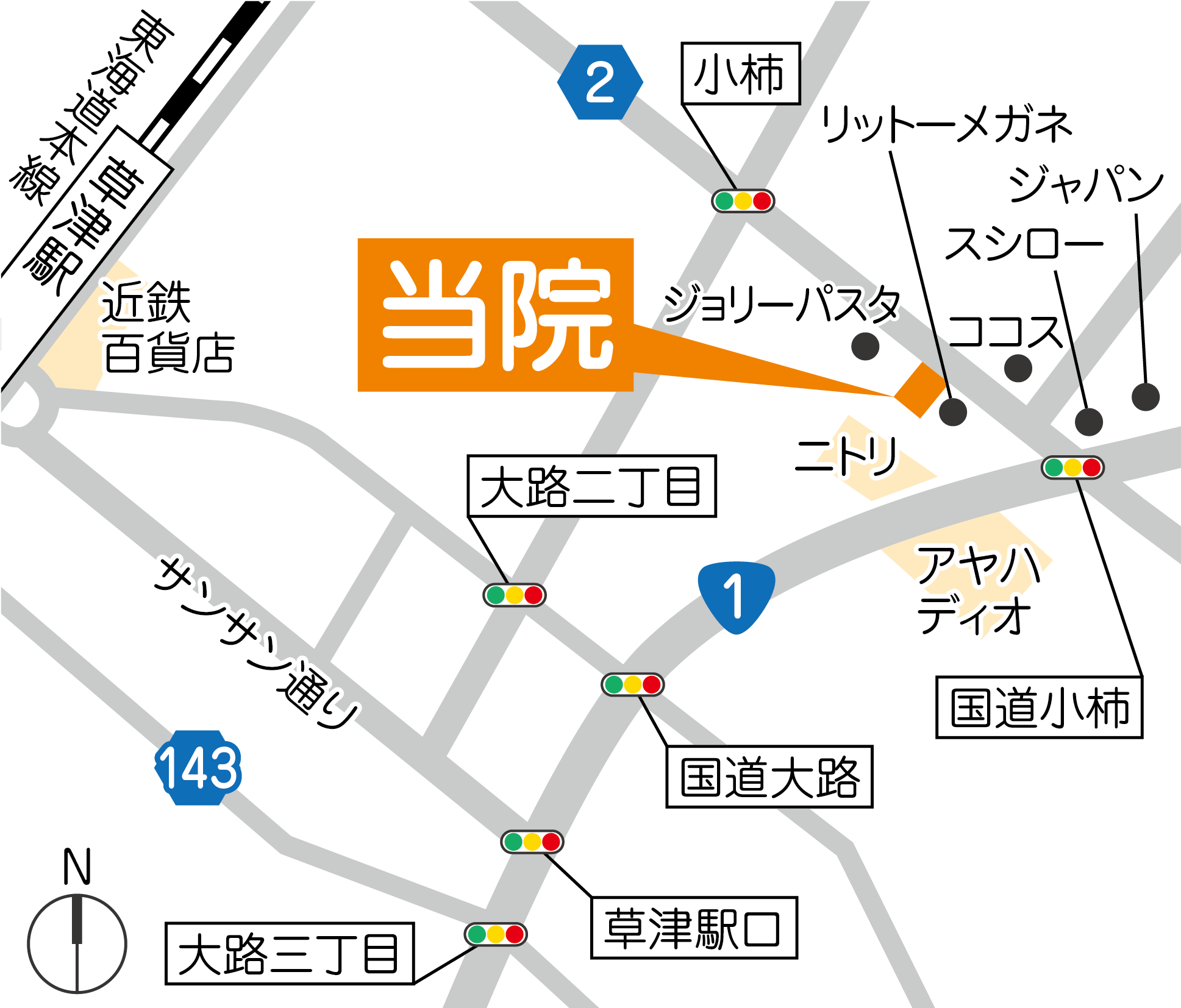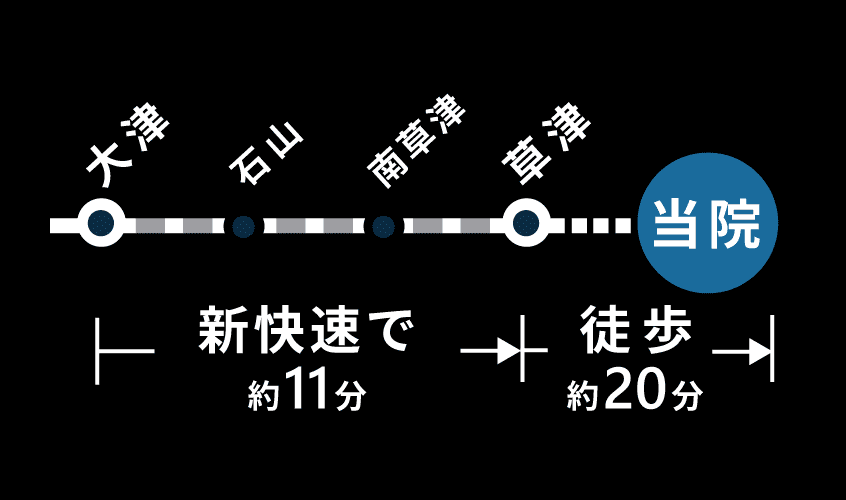脂質異常症の検査
脂質異常があるかどうかは血液検査で評価することができます
- 総コレステロール(TC)
- HDL コレステロール(HDL-C)
- LDLコレステロール(LDL-C)
- 中性脂肪(トリグリセライド: TG)
- Non-HDL-C(= TC – HDL-C)
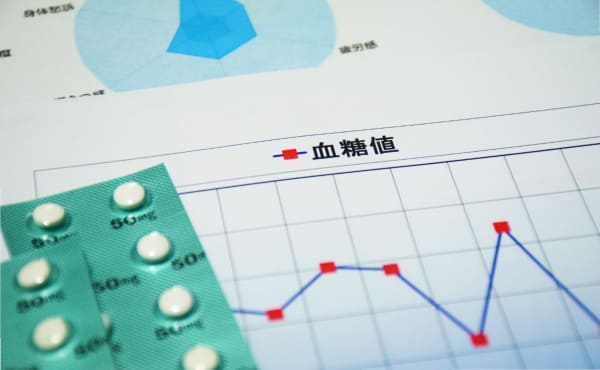
上記が脂質に該当し、健康診断や日常診療においてよく測定されるものです。
簡潔にいうと、LDL-C、TC、TGの高い状態とHDL-Cの低い状態が脂質異常であり、動脈硬化を起こします。
通常、脂質異常症が初期段階から症状を呈することは少なく、「無症状で過ごしているが健診で引っかかった」という方も多いでしょう。しかし、脂質異常のある状態では無症状であっても体内では着実に動脈硬化が進行しているのです。
健康診断における血液検査では、脂質異常についての判定基準は以下の通りです
| A(異常なし) | B(軽度異常) | C(要経過観察) | D(要受診) | E(治療中) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総コレステロール(TC) | 140~199 | 200~219 | 220~259 | ~139, 260~ | – |
| LDLコレステロール(LDL-C) | 60~119 | 120~139 | 140~179 | ~59, 180~ | – |
| HDLコレステロール(HDL-C) | 40~119 | 30~39 | ~29, 120~ | – | |
| トリグリセライド(TG) | 30~149 | 150~199 | 200~399 | ~29, 400~ | – |
この基準をもとに、健診の結果“脂質の異常あり”と診断されるのですが、健診で「医療機関の受診が必要」と判定された方全員がすぐに薬物治療(脂質を改善するお薬)開始となるわけではありません。まずは体重管理・食事療法・運動療法による改善を図ります。ただし以下に該当する場合では、専門医のもとでの薬物療法を含むきちんとした治療が必要です。
- LDL-C 180mg/dL以上 または TG 400mg/dL以上
- 生活習慣の改善を行ってもLDL-C 140mg/dL以上 または TG 300~400mg/dL以上が持続、特に高血圧・糖尿病・腎疾患の合併または脳梗塞・心筋梗塞・末梢動脈疾患の既往あり
- LDL-Cが高くないのにTCが異常に高値
脂質異常症の治療
食事療法
食事療法の目的は動脈硬化性疾患(脳梗塞・心筋梗塞など)の発症・進展を予防し、健康寿命を延ばすことです。今の食事状況を把握し、そこから改善すべき食品やメニューを理解します。また肥満のある方では、まずは3%の体重減少を目標にしましょう。
一方で高齢者では過度の食事制限による低栄養・サルコペニア・フレイルに、小児では低栄養・発育障害に注意しましょう。体重は毎日朝食前・排尿後に測定し、自身で記録し評価します。
食事の回数は1日3回を基本とし、生活パターンを考慮しながら可能な限り規則正しく同じ時刻でよく噛み時間をかけて食べるのが理想的です。「生活習慣」といわれるように、長期間継続して実践し“習慣化”できるよう無理なく行いましょう。

食事内容のポイント
- 肉の脂身、動物脂(牛脂・ラード・バター)、乳製品の摂取を抑え、魚・大豆の摂取を増やす
- 野菜・海藻・きのこ類の摂取を増やす
- 果物・ナッツ類を適度に摂取する
- 精白された穀類を減らし、未精製穀類や麦などを増やす
- 食塩を多く含む食品の摂取を減らす
- アルコールの摂取を減らす
- 食事習慣・行動を修正する
- 食品と使用中の薬物との相互作用(グレープフルーツ・納豆などは薬剤の作用に影響を与えることがあります)に注意する
- 脂質の選択
- 飽和脂肪酸を減らし、不飽和脂肪酸(特にn-3系・n-6系)を増やす。また総エネルギー摂取量(カロリー)が過剰にならないように注意する。
- 炭水化物の選択
- ショ糖(砂糖)・ブドウ糖(グルコース)・果糖(フルクトース)を摂り過ぎないようにする。
- 食物繊維を多く摂るようにする。
- 食塩摂取量
- 食塩の摂取は6g/日未満にする
- アルコール摂取量
- アルコールの摂取は25g/日未満、あるいは極力減らす
運動療法
運動療法の目的は、体力を維持もしくは増強させ、健康寿命を延ばすことです。身体活動量の多い人ほど心疾患やがんによる死亡率だけでなく、すべての死因を含めた死亡率が低いことが示されています。身体活動の不足は体脂肪の増加(肥満)・脂質異常症・メタボリックシンドローム・高血圧・糖尿病・耐糖能異常・血管内皮機能障害・体力の低下などと関連し、冠動脈疾患や非心原性脳梗塞などの動脈硬化性疾患の危険因子です。
また座りっぱなしの生活も動脈硬化性疾患の危険因子です。運動は血液中の脂質を改善し、血圧を低下させ、インスリン感受性や耐糖能を改善し、血管内皮機能の改善し血栓をできにくくします。
レジスタンス運動(ウエイトトレーニング・スクワット等)はサルコペニア・フレイル・ロコモティブシンドロームの予防に有効です。
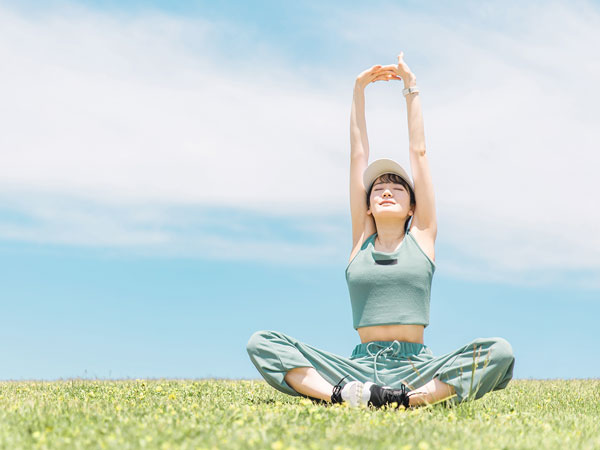
サルコペニア
加齢に伴って筋力・骨格筋量が低下して身体能力が低下し、転倒・要介護などのリスクが高くなった状態
フレイル
加齢とともに心身の活力が低下し、生活機能が障害され、ストレスに対する心身の脆弱性を示す状態(虚弱)
ロコモティブシンドローム
運動器の障害により要介護になるリスクの高い状態
薬物療法
薬物療法の適応
脂質異常症の一次予防としては食事療法・運動療法が基本ですが、LDL-C 180mg/dL以上の場合には家族性高コレステロール血症も念頭におき、生活習慣の改善とともに薬物療法が行われることがあります。
冠動脈疾患(心筋梗塞など)・アテローム血栓性脳梗塞の既往がある場合には、原則として生活習慣の是正とともに薬物療法が必須となります。
若年者や閉経前女性で動脈硬化リスクが低いと考えられる場合には、薬物療法は控えるべきです。
薬物療法の原則
まずLDL-C を低下させることがもっとも重要です。これはLDL-Cが高いことがもっとも動脈硬化に影響を及ぼし、心筋梗塞などの冠動脈疾患や脳梗塞の発症に関与するためです。次にnon-HDL-Cの低下が重要になります。LDL-Cが管理目標を達成していてもなおnon-HDL-Cが高い場合には、二次目標としてこれの低下を図ります。またTGの低下も管理目標となります。特にTG 500mg/dL以上では急性膵炎の発症リスクが高いため、食事指導とともに薬物療法を検討します。
薬物療法の実際
脂質代謝を改善させる薬剤は何種類かあり、個々の病態に応じて選択することになります。前述のように、まずはLDL-Cを低下させることが第一目標となるため、多くの場合には「スタチン」といわれる種類の薬剤を使用するケースが圧倒的に多いです。スタチン単剤で効果が不十分な場合には他の薬剤の併用を検討します。
- LDL-Cが高い場合
- HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン)
- 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬(エゼチミブ)
- 陰イオン交換樹脂(レジン)
- ニコチン酸誘導体
- プロブコール
- PCSK9阻害薬
- MTP阻害薬 ※家族性高コレステロール血症ホモ接合体のみに適応
- Non-HDL-Cが高い場合(LDL-CとTGが高い場合)
- HMG-CoA 還元酵素阻害薬(スタチン)
- 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬(エゼチミブ)
- スタチン/フィブラート系薬または選択的PPARαモジュレーターの併用
- スタチン/エゼチミブの併用
- スタチン/ニコチン酸誘導体の併用
- スタチン/n-3系多価不飽和脂肪酸の併用
- TGが高い場合
- フィブラート系薬剤または選択的PPARαモジュレーター
- ニコチン酸誘導体
- N-3系多価不飽和脂肪酸
- HDL-Cが低い場合
- HDL-Cが低い状態単独に対する有効な薬物療法はありません。しかし、多くの場合高TG血症を伴い、高TG血症の治療によってHDL-Cが上昇することから、「3. TGが高い場合」の治療と同様に治療を行います。
脂質異常症治療薬
HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン)
コレステロールの合成経路の一部であるHMG-CoA還元酵素の働きを阻害することで、肝臓でのコレステロールの合成を阻害します。そうすることで肝細胞内におけるLDLコレステロールの貯蔵が減少します。ストックが減ることで、貯蔵コレステロールを増やすべく肝細胞表面でLDL受容体(血液から肝臓へのコレステロールの取り込み口)が増加し、血液中から肝臓へのコレステロールの取り込みが促進され、結果として血液中のLDLコレステロールが低下します。
脂質異常症のほとんどの例では、スタチンが第一選択薬となります。
- プラバスタチン(主な製品名:メバロチン)
- シンバスタチン(主な製品名:リポバス)
- フルバスタチン(主な製品名:ローコール)
- アトルバスタチン(主な製品名:リピトール)
- ピタバスタチン(主な製品名:リバロ)
- ロスバスタチン(主な製品名:クレストール)
小腸コレステロールトランスポーター阻害薬(エゼチミブ)
小腸壁のタンパク質に作用してコレステロールおよび植物ステロールの吸収を阻害し、肝臓のコレステロール含有量を低下させ、血液中コレステロールを減少させます。
- エゼチミブ(主な製品名:ゼチーア)
陰イオン交換樹脂(レジン)
肝臓で生成されたコレステロールは一部が胆汁酸となり胆管から消化管内へ排泄されます。この排泄された胆汁酸の多くは腸管で再吸収され、再びコレステロールとして利用されます。陰イオン交換樹脂は胆汁酸と結合することで腸管からの再吸収を阻害し、胆汁酸の排泄量が増加します。肝臓のコレステロール貯蔵量が減るため、血液中から肝臓へのコレステロールの取り込みが増え、血液中のコレステロールが減少します。
- コレスチラミン(主な製品名クエストラン)
- コレスチミド(主な製品名:コレバイン)
プロブコール
肝臓内コレステロールの胆汁酸への異化・消化管への排泄を亢進させ、肝臓でのコレステロールの合成を抑制することで、血液中コレステロールを減少させます。
- プロブコール(主な製品名:シンレスタール、ロレルコ)
PCSK9阻害薬
肝細胞表面のLDL受容体(血液から肝臓へのコレステロールの取り込み口)を分解するタンパク質であるプロタンパク転換酵素サブチリシン/ケキシン9型(PCSK9)を阻害することで、LDL受容体が戻り血液中から肝臓内へのLDLコレステロールの取り込みが促進され、血液中コレステロールが減少します。
- エボロクマブ(主な製品名:レパーサ)
MTP阻害薬
肝臓と小腸に存在するミクロソームトリグリセリド転送蛋白(MTP)に結合してその働きを阻害します。これにより肝臓では超低比重リポタンパク(VLDL)、小腸ではカイロミクロンの形成が阻害され、血液中コレステロールが減少します。
※この薬剤は「ホモ接合体家族性高コレステロール血症」のみに保険適応があり、一般的は脂質異常症には使用できません。
- ロミタピド(主な製品名:ジャクスタピッド)
フィブラート系薬
肝臓でのコレステロールやトリグリセライドの合成阻害、血漿リポ蛋白リパーゼ(LPL)の活性化によるリポ蛋白の異化促進、胆汁内へのコレステロール排泄促進等の作用によって血液中のトリグリセライドやLDLコレステロールを減少させます。
- ベザフィブラート(主な製品名:ベザトール)
- フェノフィブラート(主な製品名:リピディル、トライコア)
選択的PPARαモジュレーター(SPPARMα)
核内受容体PPARαに結合して脂質代謝関連遺伝子の発現を調節し、血液中のトリグリセライド減少・HDLコレステロール増加効果をもたらします。
- ぺマフィブラート(主な製品名:パルモディア)
ニコチン酸誘導体
肝臓でのトリグリセライドやリポ蛋白の合成を抑制し、コレステロールの排泄を促進することで、脂質代謝を改善させます。
- トコフェロール(主な製品名:ユベラN)
- ニコモール(主な製品名:コレキサミン)
多価不飽和脂肪酸
多価不飽和脂肪酸にはさまざまな作用があり、細胞膜の構成成分であること、抗酸化作用をもつこと、抗炎症作用をもつことなど、LDLコレステロールの低下作用等があげられます。
- イコサペント酸エチル(主な製品名:エパデール)
- ω-3脂肪酸エチル(主な製品名:ロトリガ)
植物ステロール
小腸からのコレステロールの吸収を抑制します。
- ガンマオリザノール(主な製品名:ハイゼット)
配合薬
脂質異常症の病態によっては作用機序の異なる複数の薬剤を使用することが多々あり、いくつかの合剤が販売されています。いずれも使用頻度の高いスタチンとエゼチミブの合剤です。
- ピタバスタチン + エゼチミブ(主な製品名:リバゼブ)
- エゼチミブ + アトルバスタチン(主な製品名:アトーゼット)
- エゼチミブ + ロスバスタチン(主な製品名:ロスーゼット)