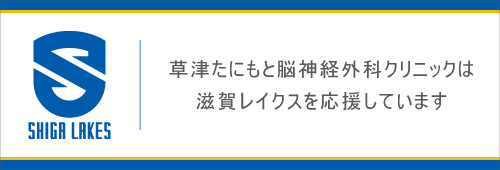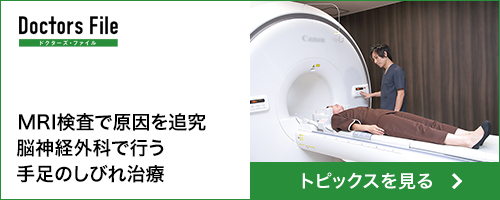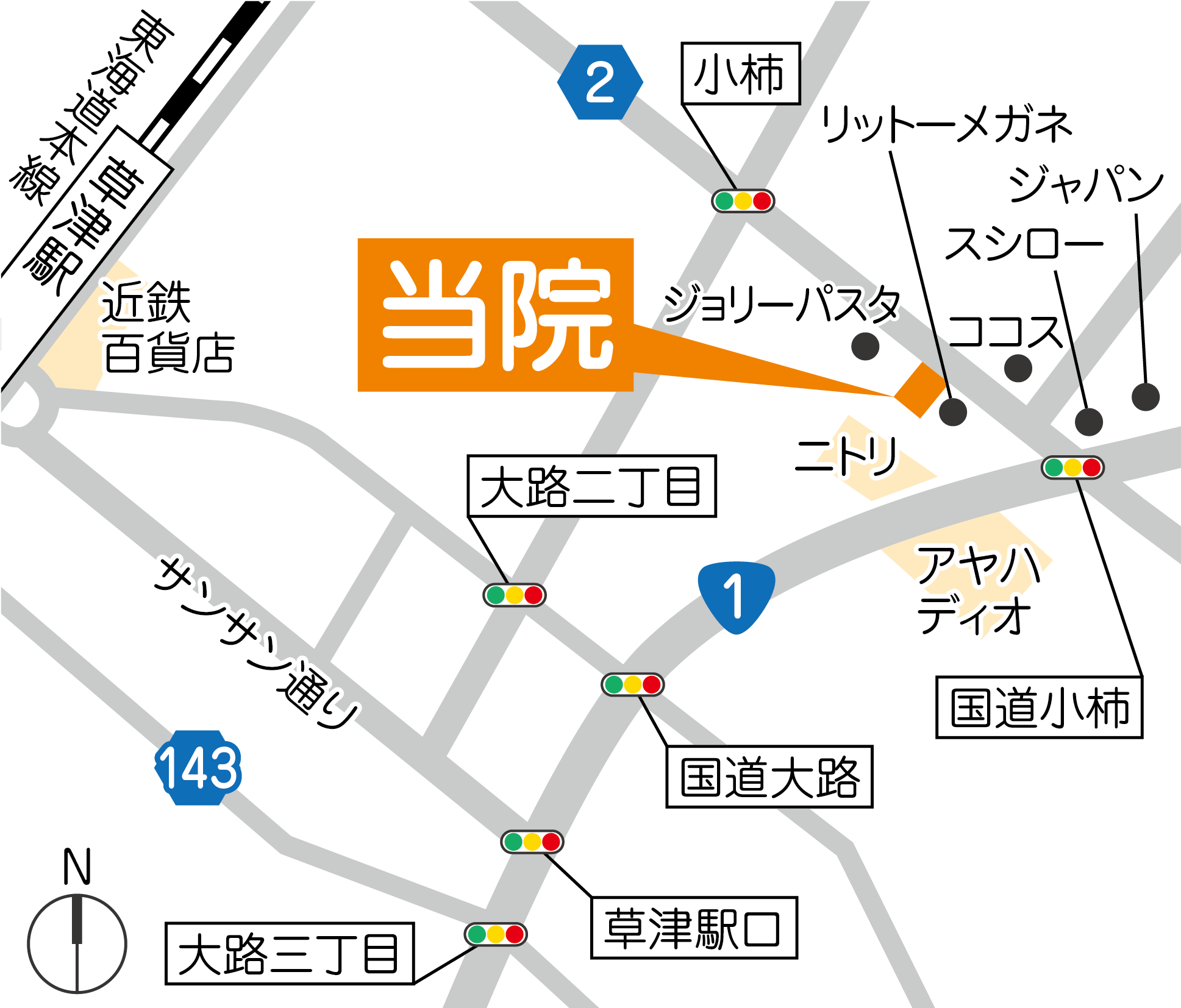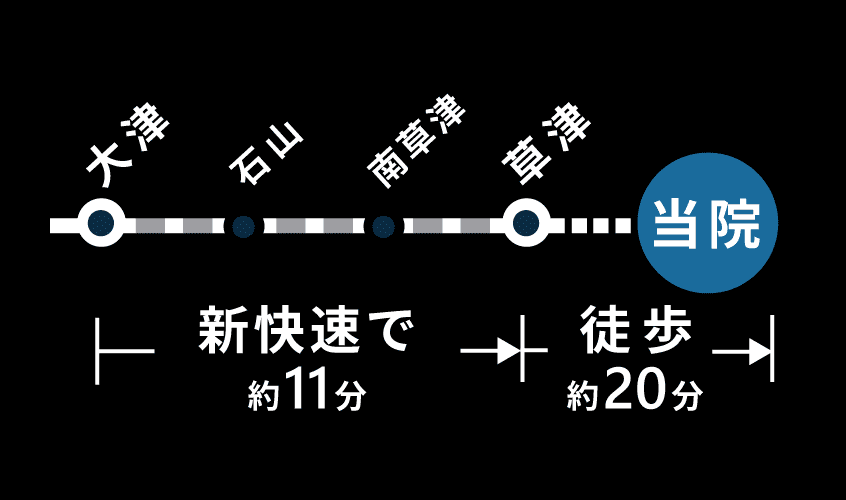脳血管の障害により起こる脳の病気を
総称して『脳血管障害』といいます
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳血管の障害により起こる脳の病気を総称して『脳血管障害』といい、一般的には『脳卒中』と呼ばれます。脳卒中により毎年多くの方が死亡したり、手足の麻痺や認知機能障害によって寝たきりとなったり大きな障害を抱えることとなったりしています。脳卒中に関してはその発症を避けることが難しい場合もありますが、食事や運動などを意識した健康的な生活習慣や、高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満・認知症といった基礎疾患をきちんと治療することで予防できるケースが多くあります。
脳卒中とは出血、梗塞にかかわらず何らかの原因により脳血管が破綻し、突然“意識障害や片麻痺などの神経学的異常をきたした状態”です

一過性脳虚血発作
あまり聞き慣れない病名かもしれませんが、きわめて重要な病気です。いわゆる“脳梗塞の前段階”であり非常に危険な状態です。実際に脳梗塞を発症した場合には総合病院などの大きな医療機関の脳神経内科や脳神経外科へ入院し治療やリハビリを行うこととなるため、クリニックにおいてはこの一過性脳虚血発作を早期に見つけ治療や生活指導を開始したり、場合によっては早期に大きな病院へ紹介したりすることが求められます。
一過性脳虚血発作では脳への血流が“一時的に“低下することで、片麻痺(左右どちらかの手足が動かしにくい)、感覚障害(左右どちらかの手足の感覚が鈍い・わからない)、失語(うまく言葉が出てこない、理解できない)や構音障害(ろれつが回らない)、視野異常(視界が欠ける、見えにくい)などといった神経症状が生じますが、血流がたまたま自然にもとに戻ることでこれらの症状も消失します。
一過性脳虚血発作を起こした方は近日中に本物の脳梗塞を発症する(今後は戻らない!)可能性が高いです。そのため一過性脳虚血発作を認めた場合には、『今回は症状が自然と治ったからひとまず大丈夫』ではなく、しっかりと精密検査を行って脳梗塞を発症する危険度を評価し、治療を開始する必要があるのです。
一過性脳虚血発作を発症した場合、その後90日(3ヵ月)以内に脳梗塞を発症することが多いです。
また1年以内の脳卒中再発率は8%です。
一過性脳虚血発作発症後早期に治療を開始した場合、90日以内の大きな脳卒中発症率が80%軽減しました。

脳梗塞
脳を栄養する血管が詰まり十分な血液が脳細胞に行き届かなくなる病気です。脳の血管のどの部分で詰まり、それによってどれぐらい広範囲の脳細胞に血液が行き届かなくなったのかや、血液が足りなくなったエリアの中に重要な機能を担っている部分が含まれているかどうか(脳のなかでも重要な部分とさほど重要でない部分とがある)によって重症度や予後が大きく異なります。
脳梗塞の起こりかたには複数のパターンがあります。
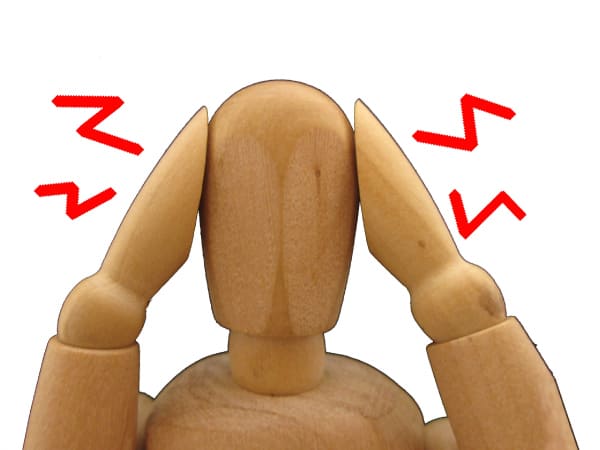
アテローム血栓性脳梗塞
脳やそこへ向かう頸部の血管の動脈硬化を基盤として生じる脳梗塞です。高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病や加齢、喫煙などによって動脈硬化が進行し、脳血管内にプラークや微小血栓が形成されることで、血液が流れることのできる有効スペースが狭くなり脳血流が低下したり血管が完全に詰まったりすることで発症します。
先述の一過性脳虚血発作『一過性脳虚血発作』は、この状態に至りかけていることを知らせる危険信号であるといえます。
心原性脳塞栓症
先述のアテローム血栓性脳梗塞と異なり、原因は心臓にあります。不整脈によって全身へ血液を送り出すという心臓のポンプ機能が障害され、心臓内で血液の流れによどみが生じ血栓が形成されます。心臓内の壁にくっついてくれている間はよいのですが、この血栓が心臓の拍動や血液の流れによってふいに剥がれ落ちると、そのまま心臓から送り出されて頸部や脳の血管のほうへ流れていきます。
すると先へ進むにつれて血管はしだいに細くなっていくので、あるところで血栓がすっぽりとはまってしまいそこで血管が完全に詰まりその先の脳へ血液が流れなくなります。こうして突然生じるのが心原性脳塞栓症と呼ばれるタイプの脳梗塞です。アテローム血栓性脳梗塞の場合には、動脈硬化によって徐々に血液が流れる有効スペースが狭くなっていくため、身体がこれを検知してあらかじめ別の脳血管ルートが発達(”側副血行路”といいます=バイパス道路工事のようなものです)し、いざ血管が詰まってしまってもその側副血行路のおかげで別ルートからその先の脳へ血液が行き届き比較的軽症にとどまる場合もあります。
これに対し、心原性脳塞栓症ではそれまで順調に流れていた血管が突然完全に詰まってしまうため身体としては全く備えができておらず、そのまま詰まったところから先のすべてのエリアに血液が行き届かなくなり、重篤となるケースが多くみられます。(もちろんこの限りではありません)
こうした心内血栓を形成し心原性脳塞栓症を起こしやすい不整脈の代表が『心房細動』です。頻繁に動悸を感じたり心電図で異常が認められたりする場合には、循環器内科を受診し、適切な治療を受ける必要があります。
ラクナ梗塞
脳の深部を流れる細い血管が詰まることで生じる脳梗塞です。“ラクナ”とはラテン語で“小さなくぼみ”を意味します。脳の深部では太い血管から枝分かれした『穿通枝』と呼ばれる細い血管が走行し脳の各部位に酸素や栄養を運んでいます。この穿通枝が詰まることで脳の深部に生じる脳梗塞がラクナ梗塞です。梗塞巣(脳細胞が壊死に陥る領域)は通常15mm未満の小さな範囲にとどまるとされます。
脳出血
脳を栄養する血管が破れて脳の内部で出血し、破れた部分の周囲の脳組織が破壊される病気です。出血した部位や出血量によって重症度や予後が大きく異なります。脳出血は頭蓋内のさまざまな原因で起こり、以下のようなものがあります。

高血圧性脳出血
脳出血の70〜90%と最も高頻度であり、同時に予防可能である重要なものとして『高血圧性脳出血』があります。その名の通り、高血圧症をはじめとする糖尿病、脂質異常症や肥満などの生活習慣病や加齢、喫煙などによる動脈硬化が原因で生じる脳出血です。実際、脳出血で救急病院を受診(搬送含む)する方のほとんどに上記を認めます。
脳のどの部位でも起こり得ますが、脳出血を起こしやすい部位があります。
視床出血
これらの部位での出血では、出血した側と反対側の麻痺や感覚障害、ろれつ困難などが生じることが多く、出血量が多い場合には意識障害を伴います。出血量が多いと、周囲の生き残った脳が血腫によって歪められてしまい“切迫脳ヘルニア“という状態になり、症状や予後がさらに悪化することがあります。こうした場合、緊急手術を行い血腫を摘出することになります。
脳幹出血
脳幹は脳の中でも生命維持に直結する機能を担う部位であり、そのため最も重篤となりやすい出血です。高度の意識障害、呼吸障害、四肢麻痺などで発症します。出血量と出血部位にもよりますが、手術などの外科的治療が困難であり、死亡されるケースも多い脳出血のタイプです。
小脳出血
後頭部痛、嘔気や嘔吐、めまい、歩行障害などで発症します。小脳は後頭蓋窩という狭いスペースに収められているため、突然生じた血腫に対応できるほどの空間的余裕が少なく、またすぐ腹側に脳幹という極めて重要な部位が存在するため、小脳出血によって脳幹のほうにまで障害が及ぶことがしばしばあり、こちらも緊急手術の対象となるケースが多くみられます。
脳皮質下出血(脳葉出血)
上記の各タイプよりも脳の表面に近い部位(白質、皮質下といいます)に生じる脳出血です。白質=皮質下と呼ばれる部分は広範囲であり、どこにどれぐらいの大きさの出血が生じたかで症状や重症度は大きく異なります。
脳アミロイド血管症
脳出血の10〜20%を占めると考えられます。脳血管壁にアミロイド蛋白という物質が沈着し、血管壁の構造が変化して脆くなってしまうことで出血します。高齢者に多く、アルツハイマー型認知症と深く関係します。また脳の血管が広範囲で脆くなるため、脳のさまざまな部位で同じような脳出血を繰り返し生じる場合もあります。出血は白質=皮質下に起こることが多いです。
その他の脳出血
その他に脳出血を生じる疾病として脳動脈瘤、もやもや病、脳動静脈奇形、硬膜動静脈瘻、脳海綿状血管腫、脳静脈洞血栓症、脳腫瘍、脳梗塞、外傷、薬剤性(抗血栓薬=血液をサラサラにする薬)、慢性腎不全(透析)などが挙げられます。
こうした病気から生じる脳出血の場合、まず起こった脳出血に対する治療を行った後、容態が安定したタイミングでそもそもの原因疾患に対する治療が必要となる場合がありますので、脳出血を起こす原因となるこうした病気が隠れていないか、しっかりと検査を行って判断しなければなりません。
くも膜下出血
約85%が脳動脈瘤の破裂により生じます。脳動脈瘤は破裂してくも膜下出血をきたすその瞬間まで無症状であることが多く、脳ドックや他のきっかけで脳MRI(MRA)を撮影しなければほとんど気づかれることはありません。しかしながら脳動脈瘤は30歳以上の成人の約3.2%(100人に3人)に存在し、比較的高頻度に認められます。
また発症好発年齢も30〜40歳台と一般的な脳梗塞や脳出血と比較して若く、重症度も高いことが多い病気です。脳動脈瘤の自然破裂率は年間約0.5〜1%ほどとされています。すべての脳動脈瘤がいずれ破裂して出血するわけではありませんが、MRIなどの検査で発見された時点ですでに非常に破裂の危険が高いと予想される脳動脈瘤もあります。残念ながら現時点で脳動脈瘤が自然と小さくなって治ってしまうことはなく、破裂や成長を阻止できるような薬剤も発見されていないため、脳動脈瘤の治療には開頭手術やカテーテル治療が必要となります。破裂の危険性が高いと考えられる脳動脈瘤を認めた場合には、早急な治療が必要である場合があるため、適切な脳神経外科を有する医療機関への紹介が求められます。
脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血を予防するためには、特に高血圧症を中心とした生活習慣病を適切に治療すること、そして喫煙および過度の飲酒を避けることが重要です。また一親等以内のご家族に脳動脈瘤あるいはくも膜下出血の方がおられる場合には、脳ドックを受診し自身に脳動脈瘤がないかを確認しておくという選択肢もあります。
くも膜下出血をきたす危険度は、現在の喫煙習慣のある方で1.9倍、高血圧症の方で2.8倍、”1週間に150g以上の飲酒をされる方で4.7倍に上昇します。
一親等以内に脳動脈瘤をもった方がおられる場合、ご自身も脳動脈瘤をもっている可能性は4%とされます。

無症候性脳血管障害
“無症候性”とは病気を患っているものの“症状がない”状態のことです。
無症候性脳梗塞
たとえば、無症候性脳梗塞とはMRI検査では小さな脳梗塞を認めるものの麻痺やろれつ困難といった症状が一切ない状態です。こうした場合、その時点では運良く無症状で済んではいるのですが、小さいながらも脳梗塞が生じていることは事実で、脳血管はかなり傷んできている、あるいは心房細動をもつ方ではごく小さな血栓がすでに繰り返し脳血管へと流れてしまっていると考えるべきです。
今回(あるいはこれまで)はたまたま症状をきたさないほどに脳梗塞が小さくて済んでいますが、近い将来寝たきりになってしまうような脳卒中を起こすかもしれません。そのため、MRI検査によって無症候性脳卒中を認めた場合には、基礎疾患を適切に治療しながら慎重に経過観察を継続するべきです。
脳卒中の既往がない65歳以上の方の場合、脳卒中の発症率はMRI検査で無症候性脳梗塞を認めなかった方よりも認めた方で明らかに高頻度であると報告されています。
同様に認知症の発症率も無症候性脳梗塞を認める方のほうが高いです。
心房細動は無症候性脳梗塞の危険因子です。
メタボリックシンドロームは無症候性脳梗塞の危険因子です。
慢性腎不全は無症候性脳梗塞の危険因子です。
無症候性脳出血
無症候性脳出血としてMRI検査でよく認められるものに『微小脳出血microbleeds』というものがあります。MRIで微小脳出血があると、特に日本を含むアジア人では将来の脳梗塞・脳出血いずれの発症リスクも高くなります。
したがってたとえば高血圧症の方が脳ドックを受診しMRI検査を行い微小脳出血を認めた場合、脳卒中の発症予防のためより厳重に血圧をコントロールしなければなりません。
微小脳出血を認める部位によって一定の病態予測が可能です。たとえば脳の深部(基底核といいます)を中心に認める場合、高血圧症や糖尿病など動脈硬化との関連を、一方で脳の比較的浅いところ(皮質や皮質下といいます)を中心に認める場合、高齢や認知症との関連を示唆します。
未破裂脳動脈瘤
30歳以上の成人において3.2%(100人に3人)に認められます。したがって人間ドック・脳ドックなどの健診MRIや、頭痛やめまいがあって病院でMRIを撮ってもらうと偶然発見されるということがしばしばあります。
未破裂脳動脈瘤は通常それ自体では症状をきたさないことがほとんど(だからこそ偶然見つかる)ですので、頭のなかに“ある”だけでは通常問題ありません。(たまに症状をきたす脳動脈瘤もあります) 問題となるのは脳動脈瘤が“破裂した“時です。脳動脈瘤が破裂すると『くも膜下出血』を発症します。こちらは一転してかなり重篤な病気です。約1/3の方は即死または短時間のうちに死亡、約1/3の方は懸命に治療がなされるものの最終的に介護を要する状態で退院、残りの1/3の方だけが自立して社会復帰できるというものです。
このように脳動脈瘤は破裂してくも膜下出血をきたす恐れがあり、まだ破れていない(くも膜下出血を起こしていない)状態の脳動脈瘤を『未破裂脳動脈瘤』と呼びます。未破裂脳動脈瘤が発見された場合、必ずしも即治療となるわけではありません。破裂する危険性がどの程度かをまず評価し、治療の適応となるかどうかを判断します。残念ながら脳動脈瘤が自然に小さくなって消失することはなく、または列を防止したり脳動脈瘤を治癒させたりするような薬剤は存在しないため、治療となると開頭手術やカテーテル治療が選択されます。
つまり脳動脈瘤の治療には一定のリスク(治療合併症の可能性)を伴うのです。したがって破裂しにくい部位の脳動脈瘤やサイズが小さな脳動脈瘤の場合には慎重に経過観察とする場合も多くあります。脳動脈瘤の経過観察は造影CT検査、MRA検査、脳血管造影検査(カテーテル検査)を定期的に繰り返して行うと同時に、生活習慣の改善(禁煙、節酒)、規則的運動の実施、高血圧を有する方では積極的な降圧治療を指導します。検査上、脳動脈瘤に経時的変化が認めない場合には経過観察の続行が可能ですが、直近の検査で脳動脈瘤の大きさや形状に変化(サイズが大きくなっている、形がいびつに変わっているなど)を認めた場合には今後の破裂の危険性が高いと評価し破裂予防のための治療が勧められますので、迅速に脳神経外科専門医を有する近隣医療機関へ紹介させていただきます。